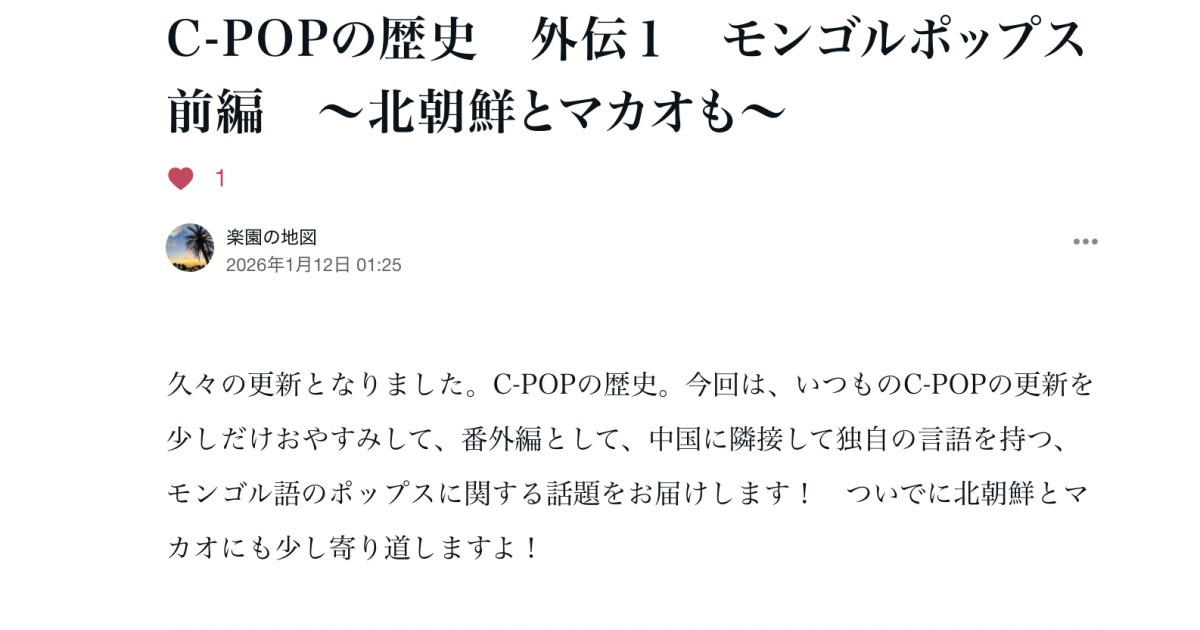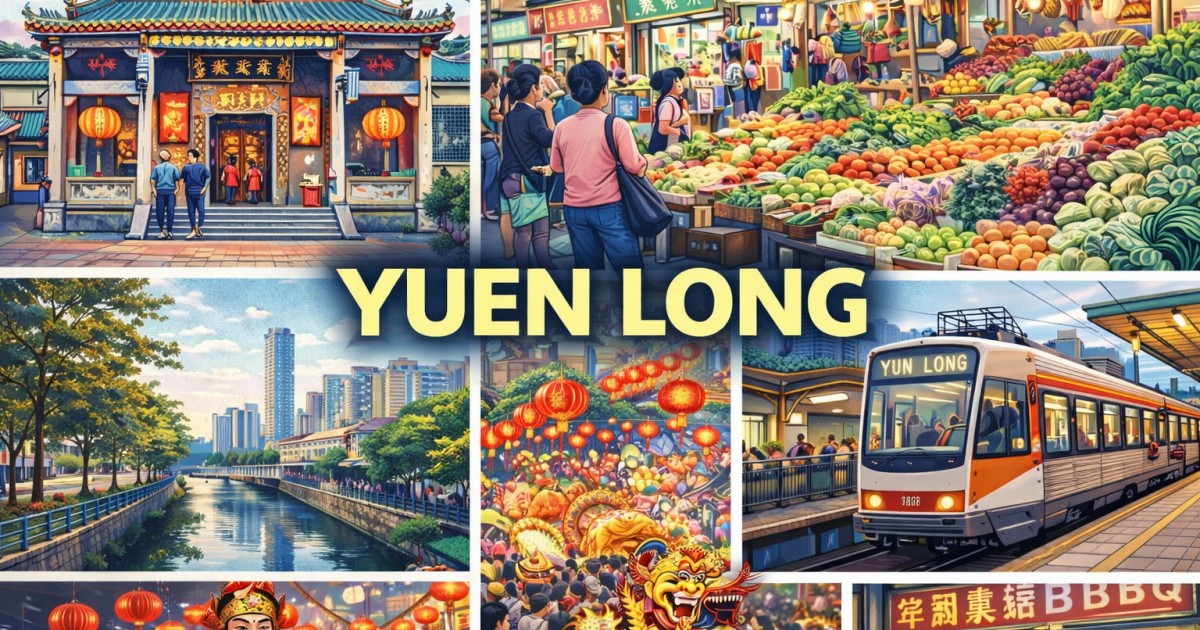楽園の地図 第84号 台湾・高雄。第二の都市が織りなすエレジーと下町グルメ
高雄/ニューヨーク/韓国/東京
船長と助手
2025.04.04
読者限定

もくじ
この記事は無料で続きを読めます
続きは、8949文字あります。
- はじめに
- 今週の楽園 高雄の下町の枯れた魅力(高雄/台湾)
- 今週のオアシス 世界各地のZARA(ニューヨーク、ボストン、ミュンヘン、メルボルン他)
- 今週楽園に行けない人のために オクジャ(韓国&ニューヨーク)
- 今週楽園で聴きたい音楽 クリスタルシティ/大橋純子(東京/日本)
- おわりに
すでに登録された方はこちら